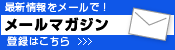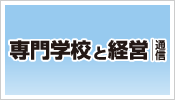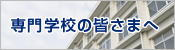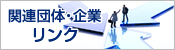学生募集から就職支援まで、最新の情報を集約。
- 専門学校と経営TOP
- 専門学校と経営通信
- 外国人材活躍推進協議会 宇佐見氏、PERSOL Global Workforce株式会社 取締役副社長 谷中氏 対談
【専門学校と経営通信】No.27
外国人材活躍推進協議会 宇佐見氏、
PERSOL Global Workforce株式会社 取締役副社長 谷中氏 対談
Q:外国人留学生の実情、変化について教えてください。
宇佐見氏:
今我々の学校には2校で600人ほどの留学生がいます。
現状としてここ数年、留学生の数が本当に増えています。現在は定員が一杯で、実際には応募者のうち半分ほどを不合格にせざるを得ない状況です。
国籍の比率も変化しており、統計にも出ていますのでご存じかと思いますが、一番多いのは中国からの留学生です。ただ、その中でも特に増えているのは、留学生だけが学んでいるコースに所属する学生です。
もちろん、日本人と一緒に学んでいる留学生もいますが、最近特に増えているのは、留学生のみで構成されたクラスに在籍する学生たちです。
2つのコースでの大きな違いは日本語力です。日本人と一緒に学ぶクラスの場合、日本語で授業を受けるため、一定以上の日本語力が必須です。最低限、授業についていけるレベルの日本語力を持っていないと参加できません。そのため、日本人と一緒に学ぶ留学生はある程度日本語力を備えています。
一方で、留学生だけのコースでは日本語力がそこまで高くない学生も多く、クラスのレベルも全体的に異なります。こうした「留学生専用コース」の需要が年々高まっており、在籍者数も急増しているのが現状です。
「留学生のみのコース」では、日本語の授業が継続して設けられています。その上で、授業は大きく日本語の授業と専門分野の授業 の2つに分かれています。イメージとしては大体半々ですが、最近はできるだけ日本語の授業の比率を減らし、専門分野の授業を増やしている状況です。
その理由は、日本語力についてはすでに企業が求める水準をある程度、満たしていることが前提とされるようになってきているからです。したがって、日本語教育だけに時間をかけるのではなく、+αとして、ビジネススキルやコンピュータ関連のプログラミングなど、より実践的な知識やスキルをしっかり身につけてもらう方向にシフトしています。
専門科目の授業も少しずつ増やしています。ただ、それでも最低限4割程度は日本語の授業を行わないと、2年間で企業が求める日本語力に到達するのは難しいのが実情です。
また、先ほどお話ししたように、最近は南アジアや東南アジアからの留学生が増えており、中国からの留学生に比べると日本語の習得スピードがやや遅い、あるいは入学時点での日本語力が低めというケースが多く見られます。そうした点が、現在の変化の一因になっていると思います。
谷中氏:
私自身も、外国人留学生がどんどん増えてきていると感じています。日本政府も2033年までに外国人留学生を40万人受け入れるという目標を掲げており、その流れは今後ますます加速するでしょう。コロナ禍で一時的に「蛇口」が閉まった状況から、再び開かれたという感覚も否めません。
産業界の立場から見ると、外国人留学生の活用にあたって日本企業には特有の課題があります。多くの企業にとって「日本語ができるのは当たり前」という意識が根強く、日本語が不十分だと採用に結びつきにくい現状があります。これは大企業だけでなく、地方の中小企業においても共通しており、大きな壁となっていると感じます。
日本語の習熟については、学生の皆さんが非常に熱心に取り組んでくださっています。私たちが専門学校の皆さまと連携を始めたのはまだ日が浅いのですが、すでに山口学園の卒業生から、日本における人材不足の分野、特に外国人材が求められる産業、たとえばインバウンド関連での活躍が見られるようになっています。
具体的には旅行業界をはじめ、バス会社、空港のグランドスタッフ、ホテルスタッフなど、多様な分野で卒業生が内定を得ています。こうした状況からも、留学生の皆さんには今後ますます活躍の場が広がっていくと考えられます。
産業界全体から見ても、日本は少子高齢化の影響で新卒採用が難しくなってきています。その中で、日本語能力の要件をクリアしていれば、外国人留学生は企業にとって非常に有望な存在とみなされ始めています。実際に企業も前向きに検討しつつある状況が見て取れるのではないでしょうか。
Q:企業が外国人留学生採用に際して抱えている課題・問題について
谷中氏:
外国人留学生の就職に関して抱えている課題については、先ほども触れましたが、やはり大きく2点あります。
1つは「言葉の壁」です。日本は他国に比べて日本語のハードルが非常に高いです。たとえ取引先が海外であっても、日本国内の組織では日本語をベースに運営されている企業が多いため、日本語ができないと職場に馴染みにくいという現実があります。
もう1つは「専門性」との両立です。留学生は専門学校などで ITや旅行、貿易などの分野で専門性を磨いています。企業もその点を大いに期待しているのですが、同時に高度な日本語力も求められてしまう。つまり「専門知識+日本語力」という2つの専門性を持つことが求められているわけです。
しかし、これを両立させるのは非常にハードルが高いということを、産業界もきちんと認識する必要があります。一方で、学校側としてはそこに挑戦していかなければならない部分もあるでしょう。私たちの役割は単に人材を紹介するだけではありませんので、企業に対しては「まずは専門性を重視し、日本語は入社後に組織の中で育成していきましょう」とお伝えしています。
もし企業が高い日本語力を求めるのであれば、専門性は入社後の育成の中で補っていくべきです。日本企業自身が教育・育成のスキルを発揮し、専門性を持った人材を成長させていく仕組みを整えていくことが大切だと考えています。
宇佐見氏:
どの企業様とお話ししても、やはり共通して出てくる課題があります。
それは「日本語力」です。ただ日本語能力試験に合格しているだけでは不十分で、企業が本当に求めているのは、例えば敬語を正しく使えること、業務指示を正しく理解できること、必要以上に聞き返さない姿勢、漢字の読み書きができることなどです。これは一見当たり前のことに思えますが、留学生にとっては非常に高いハードルです。とはいえ、企業側からすると「そのレベルでなければ採用できない」というのが実情です。
ですので、我々学校側が挑戦しなければならない課題だと考えています。特に大阪の企業からは「標準語だけでなく、大阪弁も理解してほしい」といった要望も寄せられることがあります。町工場の社長さんなどからの切実な声です。このように、日本語力に関する課題は非常に現実的で、しかも根深いものだと感じています。
そのため、我々の学校では毎年カリキュラムを見直し、単純にテキスト学習をするだけでは不十分であると認識しています。企業が求めるレベルにどれだけ近づけるか、これは学校にとって永遠の課題だと言えます。
実際、専門分野の力よりも日本語力の方がまず重視される場面が多いのも事実です。ただ、私たちは日本語学校ではありませんので、限られた2年間という期間の中で、いかに専門性と日本語力をバランスよく身につけさせるか。ここは日々研究し、試行錯誤を続けているところです。
Q:ビジネスマナーや日本独特のビジネス文化を教えるカリキュラムもありますか?
宇佐見氏:
「ビジネスマナー」と一言で言っても、その中には本当に多くの要素があります。日本人の専門学校生でも、通常は卒業学年の後期になって、就職内定が決まり社会に出る前に、必ず全学科でビジネスマナーを学びます。
今は留学生にもビジネスマナー教育を行っています。というのも、せっかく入社しても「こんなことも知らないのか」と企業から驚かれることが多々あるからです。ただ、実際に企業様からお話を伺うと、業界や業種によって求められる内容は多種多様で、一律に対応するのはなかなか難しいのも事実です。ですので、我々も日々チャレンジしながら取り組んでいる状況です。
Q:企業側から「こうしたカリキュラムがあればいい」「この部分をもっと学校で強化してほしい」といった要望やポイントはありますか?
谷中氏:
企業が求めているのは、単にカリキュラムの内容そのものよりも、学生が卒業時点でどれくらいの力を身につけているかという点です。これは即戦力レベルを求められているという意味ではありませんが、例えば IT 分野であればブロックチェーンなど最新技術の基礎を理解していて、現場での業務を通じて半年程度で一人前になれるというレベルのことです。
つまり、企業は「専門性を磨いた人材」を求めています。日本の企業は海外の有名大学の卒業生を重視する傾向もありますが、グローバルな人材の獲得競争の中で、語学力や賃金の問題もあり、海外の一流大学出身者を採用するのは現実的に難しい部分があります。そうであれば、日本でしっかり専門性を身につけた人材を採用する方が、日本企業にとっても適切なマッチングにつながるのではないでしょうか。
そのため、企業側が「海外の有名大学に引けを取らない、優秀な人材が日本国内の教育機関にいる」ということに気づいてもらえるようなスキル習得を、学生に提供することが重要だと考えています。
宇佐見氏:
我々学校側は、企業が求める人材像に少しでも近づけるよう努力しています。ただ一方で、企業側にも「外国人を雇用する」ということについて、もっと理解を深めていただきたいという思いがあります。企業が求める人材像は非常に高く、時には「完璧な人材」を期待されることもありますが、実際にはそんなに多く存在するわけではありません。むしろ、入社後に育成していくという視点が必要だと思います。
企業の皆さまには「外国人留学生を育てながら活かす」という感覚をもっと理解していただきたいと思っています。もちろんあまり強く言いすぎると反発を招く可能性もありますが、特に外国人を初めて雇用する企業にとっては、最初にその認識を持つことが重要だと感じています。
Q:外国人留学生が持つ「優位性」について、どのようにお考えでしょうか
宇佐見氏:
外国人留学生の「優位性」については、もちろん日本人学生にも意識の高い方は多くいますが、留学生は「覚悟」の面で大きな強みがあります。特に近年はミャンマー出身の学生が増えていますが、彼らは非常に真面目で、日本人に似ているとよく言われるほど勤勉です。
彼らは国の事情もあり、自分の将来を切り拓くために強い決意を持って来日しています。「日本社会で活躍し、将来は日本で暮らしていきたい」と本気で考えている学生が多く、その覚悟の強さは日本人学生以上であると感じます。
かつては「留学生はすぐ辞める」「給料が少しでも高ければすぐ転職してしまう」といったイメージがありました。確かにそうした学生も一部にはいますが、現在は全体的に真面目で意識の高い留学生が増えており、企業にとって大きな戦力になり得ます。
このように「覚悟」と「真面目さ」が、外国人留学生の大きな優位性だと思います。
谷中氏:
宇佐見先生がおっしゃったように、企業側も変わっていく必要があります。外国人材を採用したことがない企業ほど「ハードルが高い」と感じてしまいがちですが、まずは「食わず嫌い」をやめて受け入れることが大切です。実際には、外国人を採用したことのない企業が、受け入れるためにルールや体制を整えると、日本人社員の定着率向上にもつながった例もあります。
外国人留学生の優位性としては、まずモチベーションの高さが挙げられます。自国を離れて異国で頑張ろうとする強い覚悟があり、これは日本人の若者の一段上以上とも言えるほどです。外国人材は、より高い給与を求めてすぐ転職するという話もありますが、それは企業側が本人のやる気や成果に十分応えられていない側面もあると思います。この点については産業界全体で反省すべき部分もあるでしょう。
さらに、専門学校で2年間学んだ留学生には日本での生活経験があります。初めて日本に来る人は、仕事だけでなく生活全般のサポートが必要になりますが、留学生であればすでに生活基盤をある程度整えているため、企業は仕事面のサポートに集中できます。これは企業にとって大きなメリットです。
企業は外国人材を受け入れる際に「労働者を採用している」と考えてしまうのですが、実際には「生活者」を迎えているのです。ここで定着率に問題が生じます。外国人社員も日本人社員と同じように、職場では仕事を、その仕事が終わった後は、地域社会で「生活」する一員なので、生活全般の理解や慣れは重要な部分です。その点で、日本で2年間生活経験を積んだ留学生は非常に有望な人材だと言えます。
Q:専門学校だからこそ期待している点
谷中氏:
これは日本人・外国人問わず言えることですが、大学と専門学校には大きな違いがあります。大学は幅広い知識を学ぶ場であり、専門学校はより直接的に技能や専門性を高めて社会に出ていく場です。企画職の観点で見ても、大学は幅広さが特徴ですが、専門学校は実践的な力が重視されると思います。
相互補完的な意味合いもありますが、やはり「即戦力」としての期待が大きいですね。知識や技能の面で求められるのは、特に技術職や理系分野において顕著に表れています。
今後、日本の労働力不足が深刻化する中で、外国人材の方々が活躍できる分野は広がっていきます。特に技能や専門性を発揮できる産業では、力を発揮しやすい環境が整っていると思います。
ただ、日本の大企業のように「総合職一括採用」で、配属先が決まるまで分からないというスタイルではなく、例えば IT・観光・国際物流・国際貿易など、それぞれの専門分野をしっかり身につけたうえで、「私はこの分野でキャリアアップしたい」と明確に伝えられることが大切です。
そうしたスキルセットを持って社会に出ていただければ、産業界としても非常に受け入れやすいと感じます。
宇佐見氏:
専門学校にとって、先ほどの谷中さんのお話は非常にありがたい内容でした。どうしてもまず「日本語力は?」と聞かれることが多いのですが、もちろんそれは重要です。ただ、それだけでなく、専門学校ではそれぞれの専門性をしっかりと身につけてもらっています。ですので「日本語だけでなく、専門分野の力も見てほしい」という思いがあります。
専門的なスキルの習熟度は、学校ごとにかなり差が出る部分です。「この学校を出た学生はここまでできるのか」「逆に、この学校はまだここまでしかできないのか」という評価は、私たちにとって大きなモチベーションにもなります。職業教育の役割は、留学生であっても変わりません。
最終的には、専門分野の力と日本語力の両立を実現できる人材を育成し、それを産業界に送り出していきたいと考えております。
Q:最後に今後の外国人留学生の教育や雇用制度などに関する目標や展望についてお願いいたします。
宇佐見氏:
はい。我々の学園でも、日本人の18歳人口が減少していることは明らかです。国が掲げる労働力確保という観点以前に、学校が生き残るためには学生を確保することが不可欠です。その中で、留学生がこれだけ来てくださっている状況は大きな支えになっています。したがって、まずは留学生をしっかり教育し、企業が求める人材へと育てることが最も重要だと考えています。今後も留学生は増えていくでしょう。
実際、私たちの学校でも留学生が急増しており、2年前と比べて倍以上になっています。以前は1クラスだったものが、今では3クラスや4クラスにまで増えています。当然ながら学生のレベル差も大きくなってきました。日本語力だけでなく、基礎学力や専門知識にも差が出てきています。
そこで現在は、レベル別クラスやコース分けを導入し、より高度な人材を育成する層と、まずは日本で就職できるレベルを目指す層に分けて教育を行っています。例えば、同じ「留学生ビジネスコース」であっても、カリキュラムの内容や難易度を変えるなどして対応しています。中にはすでにN1を取得している学生もいるので、その実力に応じて柔軟に指導していくことが必要です。
このように、今後さらに増えていく留学生に対しては、柔軟かつきめ細かな教育体制で臨み、企業が求める人材をしっかり育成していきたいと考えています。
谷中氏:
産業界の立場から見ると、外国人材の数は今後ますます増えていくと考えています。実際に、日本の労働市場におけるサービス需要などを見ても、その傾向は明らかです。
日本の若年人口は年々減少しており、これは大学や専門学校など教育機関にとっても大きな課題です。一方で、産業界としては日々優秀な人材を必要としています。したがって、今後は外国人留学生と、日本人の新卒採用者の垣根が外れると考えています。そのタイミングは明確ではありませんが、そう遠くない未来に確実に訪れると考えています。
ただし、その時に日本企業が重視するのは、やはり自社の企業文化や組織風土です。「日本で就職するとはこういうことだ」という価値観を、外国人材の方にも理解し共有していただく必要があります。
同時に、日本の良い文化や価値を守りながら、日本企業を世界に展開させるような高い志を持った留学生や卒業生を迎え入れることができれば、日本経済にも大きな変化をもたらす可能性があります。私たちとしても、そのような人材と出会えることは非常に嬉しいですし、そうした留学生の就職支援を積極的に行っていきたいと思います。
今後も産業界全体でしっかりと連携し、外国人材とともに日本の経済を発展させていけるよう取り組んでいきたいと考えています。
<プロフィール>

宇佐見 眞也 氏
学校法人山口学園 執行役員 学園運営部長
ECCコンピュータ専門学校の教務、入試課を経て2014年に学校長就任
2023年からは現職にて学園運営の全般を統括する
学校長時代から留学生の獲得と育成に力を入れFORSAの理事としても企業から求められる留学生の人材育成を目指している。

谷中 洋治 氏
大学卒業後、大手生命保険会社を経て、2000 年テンプスタッフ(現パーソルテンプスタッフ)株式会社入社。 以後、人材派遣事業を中心に国内人材ビジネスの営業に従事。2012 年より、PT. Tempstaff Indonesia(現PERSOL INDONESIA)に取締役副社長として赴任(2014 年より同社代表取締役社長)。2016 年、パーソルグループの APAC 地域統括会社としてシンガポールに設立された PERSOLKELLY PTE. LTD.に、APAC 地域営業統括責任者として異動。13 ヶ国地域の営業統括として、グローバル企業の人事採用業務の支援に取り組む。8 年弱に及ぶ東南アジア勤務を経て、2019 年 10 月より現職。 また、政府への政策提言等を行い、各業界の発展等の事業にも積極的に関わっている。 Formatted: English (United States)